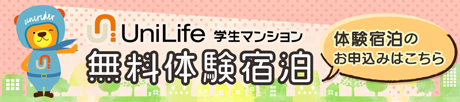第28回花園大学人権週間 講演2
後藤貞人さん紹介文
【プロフィール】
ごとう・さだと
弁護士。1947年生まれ。1975年大阪弁護士会に弁護士登録。専門分野は刑事事件。
大阪弁護士会裁判員制度大阪本部総括副本部長、日弁連裁判員本部副本部長、日弁連取調べの可視化実現本部副本部長等の活動のほか、龍谷大学法科大学院客員教授、大阪大学法科大学院非常勤講師として教鞭をとる。著書に「被告人の事情/弁護人の主張 裁判員になるあなたへ」編著(法律文化社)、「死刑と向きあう裁判員のために」分担執筆(現代人文社)など。
裁判員裁判と死刑
橋本 和明
2009年5月から始まった裁判員裁判であるが、はや5年が経とうとしている。これまでの刑事裁判とは違い、国民の中から選ばれた裁判員が裁判官(職業裁判官)とともに事件を審理することになった。この制度は裁判が身近なものとなり、国民が司法に参加していくことを目的として制定された。これまでの感想では、おおむね裁判員裁判は好評で、しだいに国民の中に定着しつつあると実感している。
しかしその一方、専門職でない裁判員が、殺人等の重大事件を担当することになったり、犯罪の事実を否認している事件を担当し、有罪か無罪かを決めなければならない。重大な事件や複雑で難解な事件ほど裁判が長期化し、裁判員に精神的な負担がのしかかることも指摘されている。さらに、事件の深刻さの影響を受け、裁判員がPTSD(外傷後ストレス障害)になったりするなど、裁判員の心のケアが必要となるケースもある。
そのなかでも、検察官から死刑が求刑される事件は、裁判員の身体的もしくは精神的な負担はことのほか高い。なぜなら、自分たちが下す判決によって、被告人の命の存否が決まるからである。その意味では、無期懲役になるのと、死刑になるのとでは、そもそも質的に大きな違いがあると言わざるを得ない。もし自分が裁判員に選ばれ、このような死刑を求刑されている事件を担当し、結果として死刑判決となったとするならばどうだろうか。おそらく死刑が執行されるまで、あるいは執行をされてからも、その裁判員は何か心に重石があるように感じてしまうのではないだろうか。
このような死刑制度についての意見は賛否両論である。また、死刑制度の存廃についてはさまざまな角度から論じられ、存続論と廃止論で考えは大きく違っている。廃止論の中には、たとえ凶悪な犯罪者であったとしてもその人権を尊重しなければならないという考えがある。一方、犯罪被害者(遺族も含む)の命や心情はどうなるのかといった立場から、死刑制度は置いておくべきだと主張する人もいる。また、社会から犯罪を防止したり、抑制させたりするためには、死刑制度を残しておくことが必要であるとの考えもある。
つまり、単純に死刑制度が良いとか悪いと決めつけるわけにはいかず、その背景には物事を根本から見つめ直す視点が必要となってくる。そして、死刑制度を考えることは、言うならば人の命や人権ということと切っても切れないものとなる。今回のテーマは、われわれがもし裁判員になり、死刑を求刑されている事件を担当したとするならばという身近な問題として、この死刑制度をどう考えればよいのかを取り上げたい。
講師としてお迎えしたのは、刑事事件のスペシャリストである後藤貞人弁護士である。同氏は刑事事件の弁護の経験から豊富な知見をもたれており、若手の弁護士の育成にも尽力を注いでおられる。筆者が知る後藤弁護士は、徹底した被告人の弁護に徹する真摯な姿勢は一貫しており、被告人やその家族に向けるあたたかなまなざしは他の弁護士を寄せ付けないほどの素晴らしいものがある。しかもそれは単なる優しさだけではなく、真実や事実を追求する厳しいまなざしをも伴うものなのである。その彼が日本の死刑制度をどのように考えているのかを花園大学にお招きして語ってもらいたい。また,死刑の求刑のある事件に弁護士としてこれまでどのように活動されてきたのかといった実践も是非お聞きし、われわれ一人ひとりの知見を深めたいものである。
(はしもと・かずあき=社会福祉学部教授)